ビジネスで成功するためには、自分に合った起業の種類を選ぶことが大切です。
「起業=法人設立」と考える方は少なくありませんが、個人事業主としての開業や副業も起業の一種です。それぞれの形態でメリット・デメリットや向いている人が異なるため、特徴を理解して最適な起業の種類を判断しましょう。
本記事では、主な起業の種類やそれぞれの違い、起業形態を選ぶ際のポイント、注意点などを解説します。
関連記事:【知らないと損】起業費用を10分の1に抑える!バーチャルオフィス活用術の全て
主な起業の種類
起業の種類は、主に以下の2つに分類できます。以下では、それぞれの仕組みやメリット・デメリットを詳しく解説します。
- 個人事業主として起業する
- 法人(株式会社・合同会社など)を設立する
個人事業主として起業する
個人事業主とは、継続・反復して事業を営む個人を指します。税務上の区分のひとつであり、管轄の税務署への開業届の提出によって個人事業主として扱われます。
個人事業主として起業する大きなメリットは、税務署への届出のみで手続きが完了し、基本的に公的費用も発生しない点です。また、個人事業主が負担する所得税は累進課税が採用されており、起業直後で所得が少ない時期は税負担を抑えやすい傾向があります。さらに、法人と比較して会計処理がシンプルであり、青色申告を活用すれば最大65万円の所得控除も受けられます。
一方、事業規模が小さく、財務状況も不透明になりやすいことから、法人と比較して社会的な信用を得にくい点がデメリットです。加えて、融資や助成金の審査でも不利になる可能性があり、所得が大きくなると税負担が重くなる恐れがあります。
これから起業を検討する際は、基本的に個人事業主としての開業がおすすめです。一度個人事業主として起業しても、法人化の制限はありません。事業規模が大きくなったり、社会的な信用力が課題となったりしたタイミングで法人化を視野に入れると良いでしょう。
法人(株式会社・合同会社など)を設立する
法人とは、法律によって個人と同様の権利義務を持つことが認められた組織を指します。以下のように多くの種類が存在し、それぞれ特徴が異なります。
- 株式会社
- 合同会社
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一般社団法人
- 一般財団法人
詳細な設立手続きは法人形態によって異なりますが、共通して法務局への設立登記が必要です。
法人として起業する大きなメリットは、個人事業主と比べて社会的な信用力が高い点です。法人登記によって存在が公的に認められ、「本気で事業に取り組んでいる」という印象も与えられます。さらに、融資や助成金の審査にも通過しやすい傾向があり、所得が大きい場合は個人事業主より低い税率が適用される点も魅力です。
ただし、設立手続きが複雑であり、公的費用も発生する点に留意しましょう。たとえば、株式会社を設立する場合、定款の作成・認証や資本金の払込み、設立登記などが求められます。さらに、各種手数料や登録免許税などで20万円以上の公的費用が必要です。
税務申告や経理の負担も重くなるため、個人事業主の開業と比較してハードルが高く感じるかもしれません。また、法人が負担する法人税には原則として累進性がないため、所得が少ない起業初期の段階では税負担が重くなる可能性があります。
このような特性から、最初から大規模な事業を展開する場合などに有力な起業形態といえます。各法人形態で特徴が異なるため、法人化を視野に入れる際は、各法人形態の特徴も確認しましょう。
主な起業の始め方
起業の始め方に着目すると、大きく以下の2つに分けられます。以下では、それぞれの始め方を詳しく解説します。
- 副業として起業する
- 本業として起業する
副業として起業する
本業で会社員を続けながら、副業として起業する方法があります。
副業として起業する最大のメリットは、起業時のリスクを大幅に抑えられる点です。副業で利益が出なくても給与収入を得られるため、生活基盤を維持しつつ、事業による損失リスクを抑えられます。また、副業が軌道に乗った段階で独立するかどうかを判断でき、本業では得られないスキルや経験を得られる可能性もあります。
ただし、本業として起業するのと比べて、事業に充てられる時間が少ない点に留意しましょう。必然的に事業規模は小さくなりやすいため、大規模なビジネスに挑戦したい方には向いていない可能性があります。加えて、副業に力を入れすぎると本業が疎かになる恐れがあり、体力的な負担も重くなるため注意が必要です。
リスクを抑えてスモールスタートできる副業ですが、なかには就業規則で全面禁止している企業も存在します。就業規則に違反すると懲戒処分が下される恐れがあるため、事前に必ず確認しましょう。
本業として起業する
本業として個人事業の開業、または法人設立を行う方法もあります。
本業として起業するメリットは、すべてのリソースを事業に注げる点です。大規模な事業にも挑戦しやすく、成功すれば大きな利益を得られる可能性があります。
しかし、副業のように給与所得を得られるわけではないため、起業のリスクは高くなります。事業で利益を得られなければ生活基盤を維持できないため、徹底した事業計画や学習意欲などが必要です。
本気で取り組みたい事業プランが存在する場合や、起業のリスクを受け入れる覚悟がある方に適した形態といえます。
起業の種類を選ぶ際のポイント
起業の種類を選ぶ際には、以下の2つのポイントに着目しましょう。以下では、各ポイントについて詳しく解説します。
- 目指す事業規模に応じて選ぶ
- 資金力とリスク許容度を踏まえて選ぶ
目指す事業規模に応じて選ぶ
自分に合った起業の種類を見極めるために、まずは目指す事業規模を明確にしましょう。
たとえば、賃貸オフィスを契約せず、自分ひとりで進められる小規模な事業を展開する場合、個人事業主や副業での起業が適しています。このようなビジネスは対外的な信用が強く求められない傾向があり、初年度から莫大な所得が発生しなければ税負担も抑えられます。
一方、初年度から莫大な資金調達を行い、従業員を雇用するような大規模な事業の場合、本業として法人を設立するのがおすすめです。副業で大規模な事業に取り組むのは現実的ではなく、法人であれば資金調達や対外的な信用力の観点から有利になりやすいためです。
事業規模と起業形態の相性が悪いと、思うように資金調達や商談が成功せず、税負担も重くなる恐れがあります。
資金力とリスク許容度を踏まえて選ぶ
資金力やリスク許容度を踏まえて起業の種類を選ぶことも大切です。
たとえば、「できる限りリスクを抑えて起業したい」と考える場合は、副業での起業が適しています。万が一事業に失敗しても会社員に戻れるため、キャリアへの傷や経済的な損失が最小限になります。
一方、「リスクを負ってでも挑戦したい事業がある」などと考える場合は、本業としての起業や法人設立も視野に入れましょう。リスクを負うことで、大規模な事業に挑戦できるチャンスや、大きなリターンを得られる可能性が広がります。
他にも、資金が不足している場合は、収入を得ながら起業できる副業や、公的費用がかからない個人事業の開業が適しているでしょう。
起業形態による税金・手続き・資金調達の違い
起業の形態によって、公的手続きの内容や資金調達の難易度などが大きく異なります。ここでは、以下の3つに着目して起業形態の違いを解説します。
- 税務・会計面の違い
- 設立・開業手続きの手間の違い
- 融資・助成金の受けやすさの違い
税務・会計面の違い
個人事業主と法人では、支払うべき税金が大きく異なります。それぞれ支払い義務のある主な税金は、以下のとおりです。
| 個人事業主 | 法人 |
| 所得税 個人住民税 個人事業税 消費税 | 法人税 法人住民税 法人事業税 消費税 |
たとえば、所得税は累進課税であり、課税所得に対して5~45%が課税されます。一方、法人税は原則として23.4%(特例で15.0%のケースあり)の比例課税方式が採用されている点が特徴です。また、個人事業主の65万円の特別控除など、青色申告で受けられる特典も異なります。
さらに、個人事業主と法人では、経費と認められる範囲も異なります。たとえば、法人では福利厚生費や社会保険料、生命保険料などが経費となりますが、個人事業主ではいずれも経費には認められません。
起業形態を選ぶ際は、負担すべき税金の税率や発生する基準、活用できる税制、経費の範囲を考慮することが大切です。
なお、副業で起業する場合でも、基本は個人事業主または法人のいずれかの税金を負担することになります。ただし、給与収入以外の所得が年間20万円以下の場合は、特例として確定申告が不要となるケースがあります。
設立・開業手続きの手間の違い
個人事業主としての開業と法人の設立手続きは、それぞれ以下のとおりです。
| 個人事業主 | 法人(株式会社の場合) |
| 管轄の税務署の開業届を提出 | 1.定款の作成 2.定款認証 3.資本金の払込み 4.法務局での設立登記 |
個人事業主は、管轄の税務署に開業届を提出するだけで開業手続きが完了し、基本的に公的費用もかかりません。開業届の提出後に社会保険や国民年金の加入手続きなどが必要となりますが、法人と比較して簡単に起業できます。
一方、法人の設立手続きは個人事業主と比べて複雑であり、株式会社の場合20万円以上の公的費用も発生します。さらに、法人設立後には税務署への届出や社会保険・労働保険関連の手続きも必要です。
ただし、法人の設立手続きは法人形態によって異なります。たとえば、合同会社の設立であれば定款認証が不要であり、公的費用も約10万円+資本金で済みます。
なお、副業として起業する場合でも、基本的に開業手続きは同様です。ただし、規模が小さく事業所得に該当しないケースなどは、特段の手続きを要しない場合があります。
融資・助成金の受けやすさの違い
個人事業主と法人で融資・助成金の受けやすさを比べると、法人のほうが審査に通過しやすい傾向があります。
法人登記を行うことで第三者からの信用や透明性が高まります。本気で事業を営むという意思も伝わりやすく、資金調達で成功できる要素にもなるでしょう。
一方、個人事業主の場合、第三者からの信頼性といった観点から法人よりも審査が厳しくなる恐れがあります。また、株式発行による出資での資金調達ができず、資金調達の幅が狭まってしまう点もデメリットです。
ただし、融資や助成金の受けやすさは、起業形態だけで決まるわけではありません。事業計画の実現性や成長性、本人の実績など、総合的に判断されます。そのため、個人事業主だからといって資金調達をあきらめる必要はありません。
起業で失敗しないために知っておきたい注意点
起業で失敗しないためには、以下の4つの注意点を事前に確認しましょう。以下では、それぞれの注意点を詳しく解説します。
- 法務・許認可を確認する
- 契約内容を慎重に確認する
- 資金管理を徹底する
- 信用を損なわないよう注意する
法務・許認可を確認する
事業運営において必要となる法務や許認可を確認しましょう。
事業運営で求められる具体的な法務は、起業形態や業種によって異なります。多くの事業者が確認すべき代表的な法律は、以下のとおりです。
- 民法
- 著作権法
- 会社法
- 労働基準法
まずは起業形態やビジネスモデルを考慮し、関連する法律は何かを判断しましょう。法務周りの知識が不足している場合、弁護士などの専門家へ相談するのもおすすめです。
また、許認可とは特定の事業を営むために必要な届出・登録・認可・許可・免許を指します。具体的には、以下のような業種で起業する場合、許認可の取得が必要です。
- 飲食業
- 美容業
- 建設業
- 宿泊業
- 運送業
- 古物商
- 士業(弁護士/税理士/行政書士/司法書士など)
許認可を取得せずに事業を開始してしまうと、厳しい罰則が下される恐れがあります。各許認可で取得要件が定められているため、許認可の要否や要件を事前に確認しましょう。
契約内容を慎重に確認する
契約を締結する際は、契約内容を慎重に確認することが大切です。不利な契約内容を提示されているにもかかわらず、よく確認せずに同意してしまうと、大きな損失につながる恐れがあります。
具体的には、契約の締結前には以下のような内容を確認しましょう。
- 自社に不利な条件は定められていないか
- 用語の意味や権利義務が明確であるか
- 必要な項目が定められているか(契約期間/支払条件/損害賠償など)
- 違法な内容が含まれていないか
- 取引の目的を達成できるか
適切に判断できるか不安な場合は、弁護士への相談を検討することをおすすめします。
資金管理を徹底する
起業で成功するためには、資金管理が不可欠です。
資金管理が疎かだと、手元の資金がショートして、取引先への支払遅延や信用の失墜を招く恐れがあります。最悪の場合、利益が出ていても資金繰りの悪化で事業の存続が困難となる「黒字倒産」となる危険があります。
さらに、事業の財務状況を適切に理解していないと、事業運営における適切な意思決定もできません。財務上のリスクを発見できず、気づいたときには手遅れになってしまう可能性もあるでしょう。
具体的に重要な資金管理の施策は、以下のとおりです。
- キャッシュフローを予測する
- 回収・支払サイクルを最適化する
- 財務状況の現状把握を徹底する
- 定期的に資金計画を見直す
適切に資金管理を行うことで、事業運営上のリスクに対して迅速に対応でき、黒字倒産や取引先からの信用の低下を防止できます。
信用を損なわないよう注意する
事業運営においては、信用を損なわないことを意識しましょう。
ビジネスは信頼で成り立っているといっても過言ではありません。取引先からの信用を失うと、取引の中止や業界での悪評を生む原因となります。また、金融機関からの信用を得られないと、十分に融資を受けられないといった事態が起こり得ます。
対外的な信用を得るためには、以下のような取り組みが重要です。
- 連絡を密に行う
- 納期を遵守する
- 企業や代表者の実績を作る
- 誠実に事業や取引先と向き合う
また、起業形態によっても他社に与える信用は異なります。たとえば、第三者からの信用が強く求められる事業である場合、法人設立での起業が効果的です。また、副業よりも本業として起業するほうが、取引先や顧客に安心感や信頼を与えられるでしょう。
加えて、事業所の住所地も信用に大きくかかわる要素です。特に自宅兼事務所で起業する場合、自宅住所だと懸念を与えてしまう恐れがあります。自宅で起業する場合でも、バーチャルオフィスなどを活用して信頼性の高い住所を公開することで、取引先や顧客からの信用を得られるでしょう。
まとめ
一言で起業といっても、個人事業主としての開業や法人設立、副業などさまざまな種類があります。それぞれメリット・デメリットが存在し、目的や事業内容、リスクの許容度などによって適切な起業形態は異なります。
これから起業に挑戦する方は、各起業形態の特徴を適切に理解して、自身の事業プランに最適な種類を選択しましょう。自分に最適な起業形態を選択できれば、リスクヘッジや税負担の軽減などにつながるため、ぜひ参考にしてください。

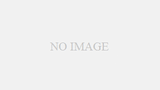
コメント