バーチャルオフィスは未だ知名度が高くないため、サービス内容や適法性といった観点で誤解されているケースが少なくありません。誤解のせいで利用を避けてしまったり、本来得られるはずのメリットを見逃してしまったりするのは非常にもったいないといえます。
バーチャルオフィスの導入に興味がある方は、誤解されやすい要素やサービスの特徴を確認し、自分に適しているかを判断しましょう。
本記事では、バーチャルオフィスのよくある誤解やメリット、導入前に確認すべきポイントを解説します。メリットを最大限に活かせれば、オフィスコストの削減や事業の柔軟性の向上などを実現できるため、ぜひ参考にしてください。
関連記事:バーチャルオフィスの誤解と安全性を徹底解説:利用前に知っておくべきポイント
バーチャルオフィスとは
バーチャルオフィスとは、事務所の所在地として公開できる住所を貸し出すサービスです。バーチャルオフィスの住所は、法人登記時の本店所在地や、名刺・ホームページに掲載する事業所の所在地として利用できます。
実際に仕事に取り組める物理的なオフィス空間は持ちませんが、その分月額数百円から数千円の低価格で利用できる点が特徴です。そのため、自宅などに物理的なオフィス空間があり、対外的に公開する信用力の高い住所を確保したい方に利用されるのが一般的です。
また、バーチャルオフィス事業者によっては、住所貸しだけでなく、以下のようなサービスも提供しています。
- 郵便物の受け取り・転送
- 貸会議室の提供
- 電話の転送
- 法人設立サポート
- 各種士業の紹介
対面での打ち合わせがある事業者や、各種サービスを用いて円滑に事業を展開したい事業者などに活用される例もあります。
バーチャルオフィスに関するよくある誤解
バーチャルオフィスは、以下のような誤解をされていることが多くあります。以下では、それぞれの誤解について、実態や正しい特徴を解説します。
- バーチャルオフィスは違法・怪しいサービス?
- 法人登記できない・信用が落ちる?
- 仕事スペースが使えないから不便?
- 郵便物の管理が不安?
誤解① バーチャルオフィスは違法・怪しいサービス?
バーチャルオフィスは違法・怪しいサービスと誤解している方がいます。しかし、実態は正規の手続きに則って合法に運営されているサービスが大半です。そのため、バーチャルオフィスの住所を公開して事業を営んでも、法人の本店所在地として登記しても問題ありません。
特定商取引法ガイドにおいても、バーチャルオフィスの住所を表示しても特定商取引法の要請を満たすと記載されています。バーチャルオフィスは適法であり、政府機関からも認められているサービスであるという裏付けとなるでしょう。
しかし、バーチャルオフィス事業者によっては、法律に則ってサービスが運営されていないケースがあります。具体的には、「犯罪収益移転防止法の定めに則った本人確認を適切にしていない」などが挙げられます。
犯罪収益移転防止法とは、マネー・ローンダリングやテロ資金の供与を防ぐことが目的として制定された法律です。バーチャルオフィスは、犯罪収益移転防止法の規制を受ける業種に指定されており、厳格な本人確認などが義務づけられています。
適切に本人確認などを行わない違法なバーチャルオフィスは、犯罪や悪用を目的とした事業者が契約している可能性があります。バーチャルオフィスの住所が悪用されると、自社の住所にも傷がつき、予期せぬトラブルや損失を招く恐れがあるため注意が必要です。
誤解② 法人登記できない・信用が落ちる?
バーチャルオフィスでは法人登記ができない・信用が落ちるという誤解があります。
実態として、多くのバーチャルオフィスでは法人登記が可能です。本店所在地の登記場所には特段の制限がなく、実際に法人登記している企業の例も多くあります。ただし、以下のような一部のケースにおいては、バーチャルオフィスでは法人登記ができない可能性があります。
- 法人登記を認めていないバーチャルオフィスである
- 同一の住所(バーチャルオフィス)に同一商号の法人が存在する
加えて、古物商や弁護士業、人材派遣業など、バーチャルオフィスでは許認可を取得できない業種の場合、開業は困難です。
また、バーチャルオフィスは都心一等地の住所を事業所として公開できることから、自宅住所よりも信頼性が高まる効果が期待できます。しかし、顧客や取引先がバーチャルオフィスに関する知識を持たない場合、不審感を与える可能性も否めません。
バーチャルオフィスを活用し、対外的な信用力を高めるためには、以下のような点を意識しましょう。
- 事前にバーチャルオフィスで開業している旨を説明する
- 犯罪収益移転防止法に則って厳格な審査を実施しているサービスを選ぶ
- 事業内容に適した住所のバーチャルオフィスを選ぶ
- 電話対応や突然の来客に対応できるバーチャルオフィスを選ぶ
「バーチャルオフィスでコストカットを実現し、安価にサービスを提供している」などと説明すれば、かえって好印象を与えられるでしょう。
誤解③ 仕事スペースが使えないから不便?
バーチャルオフィスは仕事に取り組める物理的なオフィススペースがないことから、不便とイメージする方がいます。しかし、以下のようなサービスを提供しているバーチャルオフィス事業者が多数存在します。
- 貸会議室
- コワーキングスペース
これらのサービスを活用すれば、対面での会議や打ち合わせに対応でき、物理的な執務スペースを確保することも可能です。各バーチャルオフィスで会議室やコワーキングスペースの有無が異なるため、目的に合ったサービスを選択しましょう。
ただし、バーチャルオフィスのサービス自体は、自宅などに物理的なオフィススペースがある方向けといえます。物理的な執務空間を常時使用するのが前提の場合は、シェアオフィスサービスなども視野に入れると良いでしょう。
誤解④ 郵便物の管理が不安?
物理的なオフィススペースがないバーチャルオフィスでは、郵便物を管理できないと誤解している方が多く存在します。しかし、多くの場合、専任のスタッフによる郵便物の受取・転送サービスが整備されています。バーチャルオフィスに郵便物が発送されても、わざわざ取りに行く必要はなく、自宅で受け取りが可能です。
また、バーチャルオフィス事業者によっては、郵便物の管理に関する以下のようなサービスを提供しています。
- 受取通知
- スポット転送
- 来館引取
- 簡易書留などへの代理サイン
- DM破棄オプション
これらのサービスを活用すれば、通常の事業運営と同等、または通常より快適に郵便物を管理できるでしょう。ただし、郵便物の管理体制や転送頻度、サービス内容は各バーチャルオフィスによって異なります。
バーチャルオフィスを導入するメリット
誤解している方が多いバーチャルオフィスですが、導入によってさまざまなメリットを得られます。以下では、以下の4つのメリットを詳しく解説します。
- オフィスの取得費・維持費を大幅に削減できる
- ビジネスの拠点を手軽に確保できる
- 柔軟な働き方に対応できる
- 自宅住所の公開を避けられる
①オフィスの取得費・維持費を大幅に削減できる
バーチャルオフィスの導入によって、オフィスの取得費や維持費を大幅に削減できます。バーチャルオフィスは、数千円程度の入会金と、数百円から数千円の月額料金で利用できるケースが一般的です。
一方、賃貸オフィスを契約する場合、以下のような初期費用が発生します。エリアや事業規模によって異なりますが、すべての費用を合算すると1,000万円を超えるケースがあります。
- 保証金・礼金・前家賃・前共益費
- 仲介手数料・火災保険料・保証会社利用料
- 内装工事費
- 机・椅子・通信環境などの整備費
さらに、毎月数万円から数十万円程度の固定費が発生し、資金繰りを圧迫する要因となりかねません。バーチャルオフィスを活用してコストカットを実現すれば、資金繰りに余裕が生まれ、事業の安定性や成長性が高まる可能性があります。
②ビジネスの拠点を手軽に確保できる
バーチャルオフィスを導入することで、ビジネスの拠点を手軽に確保できます。
バーチャルオフィスは費用を限りなく抑えて導入でき、審査がスムーズに進めば最短即日で利用を開始することが可能です。手軽にビジネスの拠点を確保できるため、以下のような戦略を視野に入れられます。
- 迅速に事業を展開する
- 地方にいながらも都心の住所で事業を展開する
- 試験的に都心や地方に進出する
また、一般的な賃貸オフィスと比較して解約しやすい点もポイントです。多くの場合、1〜2ヶ月程度前に通知することで解約でき、万が一事業に失敗した際でもリスクを最小限に抑えて撤退が可能です。
③柔軟な働き方に対応できる
バーチャルオフィスの導入により、柔軟な働き方に対応できるようになります。
たとえば、企業がバーチャルオフィスを導入し、勤務形態をテレワークに変更すれば、大幅なコストカットを実現できます。対面での打ち合わせや来客も、バーチャルオフィスの貸会議室や来客対応サービスを活用することで対応が可能です。
また、フリーランスとして働くノマドワーカーがバーチャルオフィスを活用する選択肢も有力です。必ずしも自宅にいるとは限らないノマドワーカーは、郵便物の受け取りや電話対応が事業運営上の課題のひとつとなります。そこで、バーチャルオフィスを導入すれば、郵便物の管理や電話の秘書サービスなどを活用でき、より柔軟に働きやすくなります。
④自宅住所の公開を避けられる
自宅で働く個人事業主や副業ワーカーがバーチャルオフィスを導入することで、自宅住所の公開を避けられます。個人事業主や副業ワーカーとして開業すると、以下のような場面で自宅住所を公開しなければなりません。
- 名刺・ホームページへの記載
- 顧客との郵便物のやり取り
- 契約書の締結
- 公的機関への届出の提出
自宅住所が第三者に知られてしまうと、プライバシーのリスクが発生します。
バーチャルオフィスの導入によって、自宅で仕事を行う場合でも公開する住所はバーチャルオフィスの所在地です。プライバシーのリスクを防止でき、安心して事業を展開できるでしょう。加えて、バーチャルオフィスの貸会議室を活用すれば、顧客を自宅に招く抵抗感にも対処できるはずです。
バーチャルオフィス導入前に確認しておきたいポイント
一言でバーチャルオフィス事業者といってもサービス内容や実態はそれぞれ異なります。バーチャルオフィスの導入前には、以下のポイントを確認しましょう。
- 提供サービスの範囲・質
- 料金体系・オプション費用の有無
- 法人登記や契約上の注意点
- セキュリティ対策
①提供サービスの範囲・質
各バーチャルオフィスによって、提供しているサービスの範囲や質が異なります。自分が必要なサービスは提供されているか、サービスの質に問題がないかを確認しましょう。そのためにも、まずはバーチャルオフィスを導入する目的や用途の明確化が重要です。
また、公式サイトに記載されている情報だけでは、サービスの質を確認することは簡単ではありません。サービスの質は、以下のような方法を活用すると把握しやすいでしょう。
- 実際に利用した方の口コミ・体験談を確認
- 各バーチャルオフィスで提供されている無料体験の活用
加えて、契約前のやり取りにおけるレスポンスの早さやスタッフの対応も大きな参考材料となります。
ただし、無料体験中に住所を公開すると、万が一サービスを乗り換える際に取引先への通知やホームページの編集などが必要となります。確実に契約すると決まっていない段階で住所を広く公開する際は注意が必要です。
②料金体系・オプション費用の有無
バーチャルオフィスの導入時は、料金体系やオプション費用の有無を確認しましょう。
バーチャルオフィスの料金は、基本的に「基本料金+オプション費用」で決まります。しかし、基本料金に含まれるサービス内容や各種オプションの費用は、各バーチャルオフィスで異なります。基本料金だけに着目していると、以下のような事態が起こりかねません。
- 基本料金に必要なサービスが含まれていなかった
- オプションを追加したら最終的な料金が非常に高額になった
バーチャルオフィスの料金を比較する際は、基本料金に加えて、基本料金のサービス内容やオプション料金を確認しましょう。また、ホームページに料金が明記されているバーチャルオフィス事業者であれば、安心して契約できるはずです。
③法人登記や契約上の注意点
法人登記の可否や契約内容も重要な確認事項です。
多くのバーチャルオフィスでは法人登記が可能ですが、なかには対応していない、または追加料金がかかるケースがあります。法人登記が目的または将来的に法人化の見込みがある場合は、法人登記の可否を必ず確認しましょう。
また、後々の不要なトラブルを避けるためにも、契約書の内容にしっかりと目を通すことが大切です。具体的には、以下のような項目を確認しましょう。
- 最低契約期間
- 解約条件
- 禁止事項
- 退会後に誤って住所を公開した際の対応
- 利用規約が変更された際の通知方法・承諾の意思表示の方法
- バーチャルオフィスの活用により被った損害への対応
契約書に目を通さないと、万が一不利な条件が記載されていても気付くことができません。また、しっかりと契約書や規約の項目が整っているかを確認することで、バーチャルオフィスの信頼性を判断できる要素となります。
④セキュリティ対策
バーチャルオフィスを安心して利用し、不要なトラブルを避けるためにも、十分なセキュリティ対策が施されているかを確認しましょう。具体的に重要なポイントは、以下のとおりです。
- 犯罪収益移転防止法に則った厳密な審査が実施されているか
- 郵便物の取引を行う際に本人確認をしているか
- 施設内に防犯カメラが設置されているか
- 複合機を使用する際は認証が求められるか
万が一情報が漏えいしてしまうと、顧客や取引先からの信頼が大きく損なわれます。セキュリティ体制については、スタッフに質問すれば把握できるケースが多いため、契約前に確認しましょう。
まとめ
バーチャルオフィスは未だ知名度が高くなく、サービス内容や適法性で誤解されているケースがあります。しかし、実態は合法なサービスであり、多くの企業がバーチャルオフィスの住所で法人登記をしています。
バーチャルオフィスの導入によって、オフィスコストの削減や柔軟な働き方の実現、プライバシーの保護などが可能です。バーチャルオフィスが自分に合っていると判断したら、各事業者のサービス内容や料金形態、契約内容を比較・検討してみましょう。

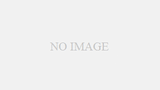
コメント