「起業家の年収はどのくらい?」と疑問を持つ方は少なくありません。
起業家の年収は、業種やビジネスモデル、業績などによって大幅に変動します。また、会社員と起業家では「年収」の仕組みや考え方が異なる点にも留意しましょう。
これから起業を目指す方は、年収の目安や会社員の給与との違いを適切に理解することが大切です。本記事では、起業家の年収の実態や会社員との違い、高年収を実現するためのポイントなどを解説します。
関連記事:起業するには:バーチャルオフィスを活用した成功ガイド
起業家の年収の実態とは
一言で起業といっても形態が多岐にわたるため、起業家の年収を一言で断言することは困難です。しかし、個人事業主や法人経営者の収入に関するデータを総合的に考慮すると、起業家の年収の実態が見えてきます。
ここでは、公的機関のデータをもとに、起業家の年収の実態を解説します。
起業家全体の平均年収
国税庁のデータによれば、令和5年時点における個人事業主(事業所得者)の平均所得金額は、483万円です。また、所得階層別の構成割合は、以下のとおりです。
| 年間所得 | 構成割合 |
| 100万円以下 | 7.9% |
| 100万円超200万円以下 | 23.3% |
| 200万円超300万円以下 | 20.8% |
| 300万円超500万円以下 | 23.9% |
| 500万円超1,000万円以下 | 16.3% |
| 1,000万円超2,000万円以下 | 4.9% |
| 2,000万円超5,000万円以下 | 2.2% |
| 5,000万円超1億円以下 | 0.4% |
| 1億円超 | 0.1% |
最もボリュームが大きい階層が「100万円超200万円以下」であり、中央値は「200万円超300万円以下」となっています。
また、国税庁の調査結果によれば、法人役員の企業規模別の平均報酬額は、以下のとおりです。
| 資本金額 | 役員の平均報酬金額(乙欄適用者を除く) |
| 2,000万円未満 | 約661万円 |
| 2,000万円以上5,000万円未満 | 約999万円 |
| 5,000万円以上1億円未満 | 約1,324万円 |
| 1億円以上10億円未満 | 約1,458万円 |
| 10億円以上 | 約2,093万円 |
| 合計 | 約849万円 |
企業規模が大きいほど、役員の平均年収も高額になります。ただし、本データはあくまで役員全体を対象とした報酬金額です。社長職や起業家本人の年収とは異なる点に留意してください。
なお、国税庁の令和5年分の調査によれば、日本の給与所得者の平均年収は460万円です。
年収の幅が大きい理由
起業後の年収は給与所得者と比べて非常に幅が大きいといえます。
事業所得者(個人事業主)の年収を例に挙げると、年収200万円未満の層が31.2%いるのに対し、年収500万円以上の層も23.9%存在します。また、大手企業の役員になると、年収2,000万円を超えるケースも少なくありません。
起業家の年収の幅が大きい理由として、業種やビジネスモデル、働き方、事業ノウハウの差があります。起業家の年収は、通常事業の業績に左右されます。たとえば、家事や育児と両立して起業に挑戦する場合、事業規模が小さくなり、年収はなかなか伸びにくいでしょう。一方、莫大な投資を行い、ハイリスクハイリターンの大規模な事業を営む場合、成功した際の利益は大きく、年収に反映されやすいでしょう。
給与所得者とは異なり、起業家の働き方は多種多様であるため、データだけで年収を判断することは簡単ではありません。その人の働き方や事業の実態などを総合的に考慮する必要があります。また、役員報酬で年収が決まる法人役員と、所得=年収となる個人事業主は単純に比較できない点に留意しましょう。
会社員の年収と何が違うのか?
起業家と会社員の年収は、仕組みや考え方が異なります。ここでは、以下の3つの視点から、起業家の年収と会社員の年収の違いを解説します。
- 固定給と成果報酬の違い
- 収入の安定性と変動性
- 税金・経費の扱いの違い
固定給と成果報酬の違い
会社員の年収は基本的に固定給です。インセンティブが採用されているケースはありますが、起業家ほど業績によって直接左右されるわけではありません。一方、起業家の年収は成果報酬の側面が強いといえるでしょう。特に、個人事業主として起業する場合は、事業の業績が所得(年収)となります。
また、事業を法人化する場合、あらかじめ決定した役員報酬が年収となります。その年の業績がそのまま年収に反映されるわけではありません。しかし、一人会社のような小規模な法人の場合、法人と代表者の財布が実質的に同じとなるケースがあります。さらに、役員報酬の金額も前年の業績に左右されやすいため、法人経営者であっても、年収は成果報酬の側面が強いといえるでしょう。
収入の安定性と変動性
会社員の年収は、安定性が特徴です。固定給が基本となる会社員の給与は、起業家ほど企業の業績に左右されません。雇用主が赤字であっても、基本的には事前に決められた収入を安定して得られます。しかし、従業員として大きな成果を上げても、急激に年収が伸びる可能性が低い点には留意が必要です。
一方で起業家の年収は、変動性が高い点が特徴です。ビジネスで成果を出した分だけ直接的に年収が増加しますが、業績が悪化すると、年収もその分減少します。会社員と比べて安定性が低い点はデメリットですが、成果を出したら莫大な年収を得られる点は魅力です。また、起業して法人を設立する場合でも、業績は翌年度以降の役員報酬に間接的に影響します。役員報酬はその年だけに着目すると変動性が低いですが、年単位で見ると会社員よりも変動性が高い性質があります。
税金・経費の扱いの違い
会社員の給与は、総支給金額から所得税や住民税、社会保険料などが差し引かれ、手取りとして振り込まれます。一方、起業家の場合、税金や手取りの取り扱いは会社員とは大きく異なります。
まず、売上として口座に振り込まれた金額「収入(年商)」から必要経費を差し引いた金額が「所得」です。さらに、所得から税金や社会保険料などを自ら支払い、会社員でいう「手取り」となります。
そのため、起業家の年収は入金された金額ベースで考えてはいけません。入金された金額から必要経費や各種税金を支払ってはじめて会社員の「手取り」と同じ扱いとなります。特に、税金の存在を失念すると、会社員よりも可処分所得が大幅に少なくなってしまうため要注意です。
また、基本的に会社員には税務上の「経費」という概念が存在しません。税金を計算する際には「給与所得控除」が考慮されますが、スーツや文具を購入しても直接的に税金が減るわけではありません。一方、起業家には「経費」という概念が存在し、事業で使った資金は収入から差し引くことができ、節税効果を発揮します。起業後には経費を有効に活用することで、税金や社会保険料の負担を最小限に抑えられます。
なお、会社員が給与から天引きされる所得税や住民税は、個人事業主が自ら支払う所得税や住民税と同じ税目です。ただし、社会保険料については厚生年金と国民健康保険で制度が異なるため、手取り金額に差が出る可能性があります。
起業家の働き方の特徴
会社員と比較した際の起業家の働き方の特徴は、以下のとおりです。以下では、それぞれの特徴を詳しく解説します。
- 自由になる一方で責任が重くなる
- 努力や工夫がそのまま成果に反映される
- 孤独やプレッシャーがある
自由になる一方で責任が重くなる
起業家になると、自由に働ける一方で責任は重くなります。
起業家は会社員とは異なり、労働時間や仕事内容を自分で決められます。仕事をしなくても誰にも注意されず、やりたくない仕事を強制されることもありません。しかし、働かなければ収入は発生しないという責任が伴います。
また、事業運営における意思決定は自分がすべての責任を負います。決断は自由にできますが、その決断が業績や事業の存続を大きく左右する場合もあるでしょう。もちろん、会社員でも責任ある立場の人はいますが、組織に属する限り、失敗の責任は上司や部署全体に分散されます。
起業する際には、自由と責任のバランスに向き合う必要があります。
努力や工夫がそのまま成果に反映される
起業して事業を運営すると、努力や工夫がそのまま成果に反映されます。
起業家の年収は、会社員のような固定給ではなく、事業の業績に大きく左右されます。つまり、営業力や商品力が高く、利益を作れれば大幅な年収アップを実現することが可能です。会社員よりも、努力や工夫で利益を創出するやりがいを感じられるでしょう。
一方、長時間働いても業績につながらなければ、事業存続の危機に陥る恐れがあります。成果主義の色が濃い働き方といえるでしょう。
孤独やプレッシャーがある
自由なライフスタイルを実現しやすい一方で、孤独やプレッシャーを感じる起業家も多く存在します。
起業家にはサラリーマンのような同期や仲間が存在しません。起業初期の段階は一人でビジネスに向き合うケースが多く、人材を雇用しても対等な目線で相談できるわけではありません。
また、意思決定を誤ると事業存続のリスクが発生するほど、起業家の意思決定には重みがあります。最悪の場合、自分や従業員の仕事が失われるといった例もあります。
孤独やプレッシャーと向き合い、重大な意思決定ができる人が起業家に向いているでしょう。
起業で高年収を実現するためのポイント
先述したとおり、起業家の年収は事業の業績に大きく左右されます。起業家として成功し、高年収を実現するためには、ビジネスでしっかりと成果を残す必要があります。
具体的に重要なポイントは、以下の6つです。以下では、それぞれのポイントを詳しく解説します。
- 市場のニーズを見極める
- 強みを活かして差別化する
- 収益モデルを最適化する
- 効率的に集客を増やす
- コストを適切に管理する
- 継続的にスキルを磨く
市場のニーズを見極める
起業で成功するためには、市場のニーズを適切に見極めることが大切です。
どんなに自分自身で取り組みたい事業内容であっても、市場にニーズがなければ決して成功はできません。ニーズの有無を見極める代表的な方法は、以下のとおりです。
- Googleトレンドなどで検索ボリュームを調べる
- SNSでユーザーの反応を探る
- 競合他社の有無を調査する
- Amazonや楽天のレビューを確認する
ニーズがあると判断したら、より詳細にニーズを持っているユーザーの属性を判断しましょう。ニーズを持つユーザーの性別や年齢、関連する興味関心を把握すれば、適切なマーケティング戦略を練りやすくなります。ユーザー層の把握では、SNS分析ツールの活用やアンケート調査、SNS広告の出稿によるABテストなどが効果的です。
強みを活かして差別化する
強みを活かして差別化を行うことで、価格競争からの脱却やブランド力の強化、利益率の向上などが期待できます。
差別化とは、競合他社にはない独自の価値を提供して優位性を確立する戦略です。特に、自社の強みを活かした差別化は、競合他社が真似しづらく、より強力なブランドイメージを確立できます。
ここで挙げられる強みとは、技術力の高さや人脈・コネクション、既存顧客の活用などです。まずは、以下のようなフレームワークを活用して、自社の強みや市場、競合他社を分析しましょう。
- SWOT分析
- 3C分析
- STP分析
収益モデルを最適化する
収益モデルとは、利益を出すための収益の流れや構造を指します。代表的な収益モデルは、以下のとおりです。
- 売り切り型
- サブスクリプション型
- 広告モデル
- マッチング型
- フリーミアム型
収益モデルに穴があると、商品やサービスが優れていても、うまくマネタイズできない恐れがあります。最適な収益モデルは、提供する価値やターゲット層によって異なります。収益モデルの最適化を実現するために、以下のような点を意識しましょう。
- ターゲットを明確にする
- 無駄なコストや工程を削減する
- 課金や購入までの導線を整備する
- 人気商品やユーザーの興味関心を調査する
- 顧客生涯価値を最大化する
効率的に集客を増やす
事業の売上を伸ばすためには、効率的に集客を増やすことが大切です。代表的な集客方法は、以下のとおりです。
- ホームページ・オウンドメディアの運用
- SNSアカウントの運用
- Web広告の配信
- メールマガジンの配信
- インフルエンサーマーケティング
- チラシ・ダイレクトメール
- オフラインイベントの開催
集客時には、費用対効果を意識しましょう。集客に多額のコストを投じて売上が伸びても、広告宣伝費を考慮すると赤字になっては本末転倒です。それぞれの集客方法の特徴を理解し、ターゲットユーザーや商品・サービスを踏まえた施策を取り入れることが重要です。
また、起業直後で資金繰りに課題を感じる場合、低コストで集客できる施策を選択しましょう。具体的には、Webサイトの運営やSNSアカウントの運用などは費用を抑えつつ、長期的な集客効果が期待できます。
コストを適切に管理する
起業で成功するためには、徹底したコスト管理が重要です。ビジネスにおいて、利益は「売上高-費用」で決まります。つまり、コストを最適化することで、利益の最大化につながります。
ただし、単にコストカットすれば良いわけではありません。たとえば、より安価な原材料にした結果、商品の品質が下がり、顧客離れが進んだら本末転倒です。いかに利益率を高めるかが重要となります。
具体的に効果的な施策は、以下のとおりです。
- 綿密に予算を設定する
- 業務の自動化・効率化を進める
- 支出項目をリスト化する
- コストカットは固定費の削減から検討する
- 定期的な効果測定を実施する
- 在庫管理を最適化する
- 外注を有効活用する
継続的にスキルを磨く
起業で高年収を達成するためには、起業後も継続的にスキルを磨くことが大切です。
昨今はユーザーニーズの多様化やIT技術の発展などにより、ビジネスの世界は目まぐるしく変化しています。常に最新の情報やノウハウを学び、取り入れることでビジネスを成長させ続けることができます。起業後のスキルアップは、セミナーやワークショップへの参加、メンターの活用、実務を通じた学習などによって可能です。
また、新たに習得したスキルやノウハウを積極的にビジネスに取り入れる柔軟性も求められます。起業後のスキルアップをおろそかにしたり、古いやり方に固執したりすると、環境の変化に適応できず、業績は右肩下がりとなってしまうでしょう。
起業と年収のリアルから見える選択肢
起業すべきか、会社員として働くべきか悩んでいる方は、以下の3つを考慮することが大切です。ここでは、それぞれのポイントを詳しく解説します。
- 年収以外の価値を考える
- 自分の適性を見極める
- 長期的なキャリアを描く
年収以外の価値を考える
起業を検討する際は、年収以外の価値を考えることが大切です。年収だけに囚われてしまうと、自分が本当にやりたい仕事や、将来のビジョンを見失ってしまう恐れがあります。また、事業がうまくいかなかった際に挫折してしまう原因となり、仕事自体が苦痛となる可能性もあるでしょう。
起業には年収以外にも以下のような価値・やりがいが存在します。
- 自分のアイデアや理想を形にできる
- 自分が好きなこと・得意なことを仕事にできる
- 社会に貢献している実感を持てる
- ビジネスを自分の意思決定でコントロールできる
- 働き方やプライベートの過ごし方を柔軟に決められる
これらのやりがいやメリットに魅力を感じられれば、起業に挑戦する価値は十分にあるでしょう。一方、お金以外の価値に気付けない場合は、自分自身の価値観を見つめ直し、起業すべきかを慎重に判断することをおすすめします。
自分の適性を見極める
自分の適性が起業に向いているかどうかを判断しましょう。たとえば、以下のような方は、起業家としての働き方が向いている傾向があります。
- 自分の責任の下で重要な意思決定ができる
- 収入が大きく増減してもストレスにならない
- 孤独やプレッシャーとうまく付き合える
- 目標や目的に向かって日々努力ができる
- 継続力があり、失敗から学べる
一方、以下のような方は起業家としての適性がない可能性があります。
- 指示されたことしかできない
- 孤独やプレッシャーには耐えられない
- できる限り責任を負いたくない
- お金の管理ができない
- 計画性がない
起業したからといって必ずしも幸せになれるとは限りません。自分には起業が向かないと判断したら、潔く起業をあきらめることも大切です。
長期的なキャリアを描く
起業すべきかどうかを判断する際は、長期的なキャリアを描くことが大切です。一例ですが、少なくとも以下のような点は考慮すべきでしょう。
- 最終的に目指す専門性・働き方
- ライフイベント(結婚/自宅購入/子育て/介護など)
- 事業プランの将来性
- 起こり得るリスクと将来への影響
目先の利益は見込めても、事業プランの将来性や将来のライフイベントを考慮すると、起業すべきではないケースがあります。また、独立ではなく副業として起業に挑戦する選択肢も生まれるはずです。
一度起業したら、その後に会社員に戻ることは簡単ではありません。10年後・20年後の自分の姿をイメージして、意思決定を行いましょう。
まとめ
起業家の年収は、個々の働き方や業種、ビジネスモデルなどによって大きく異なります。年収は成果報酬が基本であり、事業で成果を出せば一気に年収が増えることも十分にあり得ます。一方で、変動性が高いという注意点があり、業績が悪ければいくら働いても年収が増加しません。
ビジネスに取り組むからには、「いかにして利益を創出するか」は非常に重要な課題です。起業家として活躍し、十分な収入を得るためにも、収益モデルの最適化や徹底したコスト管理、日々のスキルアップなどを徹底しましょう。
また、起業すべきか悩んでいる方は、年収以外の価値を考慮することが大切です。自分の適性や長期的なキャリアを踏まえ、起業すべきか、会社員として活躍すべきかを判断しましょう。

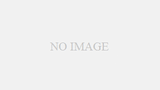
コメント