バーチャルオフィスの住所は、開業届への記載や法人登記、特定商取引法に基づく表記など、さまざまな場面で活用できます。バーチャルオフィスの住所を有効活用すれば、プライバシーの保護や対外的な信頼性の向上、オフィスコストの削減が期待できます。
しかし、バーチャルオフィスの住所が使えないケースや注意すべきポイントも存在するため、注意が必要です。活用できるケースや住所利用のポイント、注意点などを把握し、自分に最適なサービスであるかを判断しましょう。
本記事では、バーチャルオフィスの代表的な用途や注意点、住所利用のポイント、メリット・デメリットなどを解説します。
関連記事:バーチャルオフィス住所の完全ガイド:利用のメリットとデメリット
バーチャルオフィスの住所が使える代表的な用途
バーチャルオフィスは、事業運営で住所を公開する幅広い機会で利用できます。代表的な用途は以下のとおりです。
- 企業の本店所在地として法人登記を行う
- 個人事業主の開業届に記載する
- 請求書・見積書・契約書などの証憑書類に記載する
- 名刺・ホームページ・会社案内などに記載する
- 特定商取引法に基づく表記として公開する
オフィスの実態を伴わないバーチャルオフィスでも、問題なく法人登記や開業届への記載が可能です。また、請求書・契約書や名刺・ホームページへの記載など、利用規約や法令に違反しない範囲であれば、柔軟に住所を公開できます。
バーチャルオフィスの住所が使えない・注意が必要なケース
バーチャルオフィスの住所は、すべての場面で自由に公開できるわけではありません。具体的には、以下のようなケースでは、バーチャルオフィスの住所を利用できません。
- 法令や公序良俗に違反している場合
- バーチャルオフィスでは取得できない許認可が必要な場合
- バーチャルオフィス内に同一商号の企業が存在する場合
- 利用規約に違反している場合
法令や公序良俗に違反している場合とは、「詐欺やマネー・ローンダリングが目的」や「住民票の住所として利用」などが挙げられます。また、同一住所に同一商号の企業が存在すると、法人登記が認められません。さらに、物理的なオフィス空間が求められる許認可を取得する場合、バーチャルオフィスでは却下される可能性が高いため要注意です。
加えて、各事業者で「法人登記は非対応」などの規約が定められている場合があります。候補のバーチャルオフィスを個別に確認することが大切です。
法人登記・開業届・特商法での住所利用のポイント
バーチャルオフィスを活用する目的によって、住所利用のポイントが異なります。以下では、次の3つの用途について、それぞれ住所利用のポイントを解説します。
- 法人登記での住所利用のポイント
- 開業届への記載での住所利用のポイント
- 特定商取引法に基づく表記での住所利用のポイント
法人登記での住所利用のポイント
バーチャルオフィスの住所は、基本的に法人登記時の本店所在地として利用できます。しかし、以下の2つのケースにおいては法人登記が認められないため、注意が必要です。
- バーチャルオフィス事業者が法人登記での利用を禁止している
- 同一のバーチャルオフィス内に同一商号の法人が存在する
バーチャルオフィスによっては、法人登記を禁止している場合があります。また、法人登記が認められている場合でも、登記時の住所を指定している(ビル名まで記載など)ケースがあります。事前に利用規約を確認し、法人登記の可否や住所の指定などを把握しましょう。
また、同一住所に同一商号の法人が存在する場合、法人登記は認められません。国税庁の「国税庁法人番号公表サイト」などを活用し、同一商号の利用者が存在しないかを確認しましょう。
バーチャルオフィス事業者のなかには、法人設立サポートや法人口座開設サポートを提供しているケースがあります。法人登記が目的の場合は、これらが提供されているサービスを視野に入れると良いでしょう。
開業届への記載での住所利用のポイント
バーチャルオフィスの住所は、個人事業主・フリーランスの開業届にも記載できます。ただし、開業届に記載しただけでは、原則として納税地としては扱われません。あくまで事業所としてバーチャルオフィスの住所を届け出た扱いになります。
バーチャルオフィスを納税地に設定したい場合は、開業届の提出後に以下のいずれかの手続きが必要です。
- 「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出
- 確定申告書の「納税地」欄にバーチャルオフィスの住所を記載
バーチャルオフィスを納税地に設定すると、国税関係の書類がバーチャルオフィス宛に発送されます。また、確定申告先もバーチャルオフィスを管轄する税務署となるため、利便性などを考慮して選択しましょう。
なお、個人事業主の納税地は原則として住所地であり、事業所を納税地に設定するのはあくまで特例扱いとなります。詳しい取り扱いは管轄の税務署に確認するのが安心でしょう。
特定商取引法に基づく表記での住所利用のポイント
特定商取引法とは、消費者と事業者間のトラブルが発生しやすい取引について、消費者保護を目的とした一定の規制を定めた法律です。ネットショップ運営などが規制対象であり、「特定商取引法に基づく表記」として事業者名や所在地の公開が義務づけられています。
バーチャルオフィスは特定商取引法に基づく表記にも利用できます。しかし、特定商取引法の要件を満たすためには、「現に活動している住所」でなければなりません。具体的には、以下のようなケースでは、特定商取引法違反とみなされる恐れがあります。
- バーチャルオフィスの住所に発送した郵便物を受け取ってもらえない
- 完全無人運営であり、住所地を訪れても事業者と一切連絡が取れない
特定商取引法に基づく表記で住所を利用したい場合は、郵便物の転送や窓口受付、受付システムなどを提供しているサービスを選択しましょう。
バーチャルオフィス住所利用のメリット
バーチャルオフィスの住所をビジネスに活用する主なメリットは、以下の4つです。以下では、それぞれのメリットについて詳しく解説します。
- プライバシーを保護できる
- 対外的な信頼性を得られる
- オフィスコストを削減できる
- 都心・地方進出がしやすくなる
プライバシーを保護できる
バーチャルオフィスの住所の公開によって、プライバシーの保護が可能です。自宅兼事務所で事業を営む場合、以下のような場面で自宅住所が取引先や顧客に伝わります。
- 請求書や見積書、契約書の作成
- 郵便物のやり取り
- 名刺・ホームページへの記載
- 公的機関への届出の提出
- 法人登記
結果的にプライバシーのリスクにつながり、最悪の場合、嫌がらせやストーカー被害が発生する恐れがあります。
バーチャルオフィスの住所を公開すれば、上記のようなプライバシーのリスクを防止可能です。安心・安全に事業を運営できるようになるでしょう。
対外的な信用を得られる
バーチャルオフィスの都心一等地の住所を事業所として公開すれば、対外的な信用を得られる可能性があります。
アパートや一軒家の住所を事業所として公開すると、取引先に「本当に事業に取り組んでいるのか」と懸念を与えるかもしれません。地方や田舎の住所でも、活発にビジネスを営んでいるという印象は持ちにくいでしょう。
一方、都心一等地の住所であれば、ビジネスの印象が強く、「本気で事業を営んでいる」という印象を与えられます。ECサイトで同じ商品を取り扱っていても、事業者の住所が都心一等地と自宅住所では、前者のほうが消費者は安心して購入できるはずです。
結果として、成約率の向上や取引の長期化などが見込めます。
オフィスコストを削減できる
バーチャルオフィスの住所を事業所や本店所在地にすることで、オフィスコストを大幅に削減できます。
一般的な賃貸オフィスを契約すると、数十万円から数百万円程度の初期費用や、月額数万円から数十万円の固定費が発生します。一方、バーチャルオフィスであれば、数千円程度の初期費用と、月額数百円から数千円程度の固定費でオフィスを取得可能です。
現在、物理的なオフィスを契約している方でも、リモートワークを導入すればバーチャルオフィスでも問題ないことがあります。バーチャルオフィスの郵便サービスや電話サービス、貸会議室などを活用すれば、より効率的に事業を運営できるでしょう。
オフィスコストを削減すれば、資金繰りの安定化や起業リスクの抑制などを実現可能です。
都心・地方進出がしやすくなる
バーチャルオフィスの活用によって、都心・地方進出がしやすくなります。
バーチャルオフィスは比較的簡単に事業用の住所を取得可能で、契約後すぐに利用を開始できるため、手軽に複数の拠点を持つことができます。さらに、短期契約できるサービスが多いため、都心・地方進出が軌道に乗ったタイミングで賃貸オフィスへの切り替えも可能です。
数千円程度の初期費用で新たな拠点を持てるため、万が一失敗しても経済的な損失は最小限に抑えられます。リスクを最小限に抑えつつ、スピーディーに支店や支所を展開できるため、リスクヘッジや事業運営の効率化につながります。
バーチャルオフィス住所利用のデメリット
バーチャルオフィスの住所利用には、以下のようなデメリットが存在します。以下では、それぞれのデメリットについて詳しく解説します。
- 取引先や金融機関に警戒心を与えてしまう可能性がある
- 取得できない許認可が存在する
- 契約時には厳格な本人確認・審査が実施される
取引先や金融機関に警戒心を与えてしまう可能性がある
バーチャルオフィスは物理的なオフィス空間を持たず、事業の実態を確認しにくい特徴があります。また、利用者全員が同じ住所を使うため、Web検索を行うと複数の事業者が表示されます。
バーチャルオフィスの仕組みを理解していない事業者にとって、懸念を生む材料になり得るでしょう。事前にバーチャルオフィスの住所である旨や、仕組みを説明することが大切です。
また、過去には詐欺やマネー・ローンダリングなどの悪用目的でバーチャルオフィスが活用された事例が多発しました。このような背景から、金融機関は自社の銀行口座が悪用されるのを防ぐために、厳しい審査を実施する傾向があります。バーチャルオフィスでも法人口座の開設は可能ですが、事業の実態を厳しく確認される点に留意しましょう。
取得できない許認可が存在する
バーチャルオフィスの住所では取得できない許認可が存在します。具体的には、事業の実態を確認できる物理的なオフィス空間が求められる許認可は、基本的にバーチャルオフィスでは取得できません。
そのため、以下のような職種はバーチャルオフィスでの開業が難しいため注意しましょう。
- 古物商
- 税理士・弁護士・司法書士を含む一部の士業
- 有料職業紹介業
- 人材派遣業
- 建設業
- 探偵業
事業運営において許認可の取得が必要な場合は、事前に取得要件を確認したうえで適切なオフィス形態を選択しましょう。
契約時には厳格な本人確認・審査が実施される
バーチャルオフィスの契約時には、厳しい本人確認や審査が実施されます。
バーチャルオフィスは犯罪収益移転防止法の規制を受ける業種であり、適正な本人確認や審査が義務づけられています。犯罪収益移転防止法とは、マネー・ローンダリングやテロ資金供与といった犯罪行為を防止するための法律です。また、事業概要の確認や対面での面談を実施している事業者も多く存在します。
バーチャルオフィス事業者に悪用のリスクがあると判断された場合、利用は許可されません。本人確認ができ、事業の概要や誠実な姿勢が伝われば問題なく通過できることが多いですが、一定の事前準備が求められます。
なお、犯罪収益移転防止法に違反した簡易的な入会フローとなっているバーチャルオフィスも存在しますが、入会は避けるのが無難です。悪用目的で入会する者が存在する恐れがあり、自社の評判まで損なわれる危険があります。安心・安全にバーチャルオフィスを活用するためにも、適正な手続きで審査を実施している事業者を選択しましょう。
バーチャルオフィス契約前に確認すべき住所利用条件
バーチャルオフィスの住所利用の条件は、各事業者で異なります。バーチャルオフィス事業者によっては、利用規約で以下のような制限を設けている場合があります。
- 法人登記は禁止
- 法人登記の住所は事業者が指定
- バーチャルオフィスである旨を公表してはいけない
また、法人登記が認められていても、上位プランへの加入や追加料金を求められることも少なくありません。バーチャルオフィスの契約前には、法人登記の可否や住所利用の制限、追加費用の有無などを確認しましょう。
まとめ
バーチャルオフィスの住所は、法人登記や請求書・契約書への記載、名刺・ホームページへの公開など、幅広い用途で活用できます。有効に住所利用ができれば、プライバシーの保護や信頼性の向上、コストカットを実現可能です。
ただし、バーチャルオフィスでは取得できない許認可があります。また、物理的なオフィスが伴わないという特性上、取引先や金融機関に懸念を与えてしまう恐れもあります。特徴やメリット・デメリットを適切に把握し、バーチャルオフィスを利用すべきかどうかを判断しましょう。
バーチャルオフィス事業者は多岐にわたり、それぞれ特徴が異なります。まずはバーチャルオフィスの利用目的や予算、活用したいサービス内容を明確にして、最適な事業者を選択しましょう。

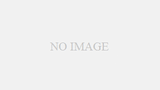
コメント