「バーチャルオフィスは違法・怪しい」と誤解している方は少なくありません。
結論からいえば、バーチャルオフィスは適法なサービスです。有効活用すれば、コストカットやプライバシーの保護、取引先・顧客からの信頼性の向上など、さまざまなメリットを得られます。
しかし、バーチャルオフィスが詐欺やマネー・ローンダリングなどで悪用されている場合は、当然違法となります。実際、バーチャルオフィスの悪用事例は散見され、仕組みを理解していない方に怪しいという印象を与えるケースも少なくありません。
本記事では、バーチャルオフィスの適法性や違法となるケース、安心して利用するための注意点・選び方などを解説します。バーチャルオフィスを安全に活用し、対外的な信用を得るためのポイントが理解できるため、ぜひご覧ください。
バーチャルオフィスは違法?
誤解されることがありますが、バーチャルオフィスは違法性のないサービスです。しかし、用途によっては違法性が生じる可能性があります。
以下では、バーチャルオフィスの違法性について詳しく解説します。
バーチャルオフィスそのものは合法なビジネスモデル
法人・個人事業主にかかわらず、バーチャルオフィスの利用自体には違法性はありません。
違法と勘違いされる理由として、住所地に物理的なオフィスがないことが挙げられます。しかし、法人の本店所在地や個人事業主の事業所には法的な制限がなく、バーチャルオフィスでも適法に登記・開業が可能です。また、特定商取引法に基づく表記において、バーチャルオフィスの住所の記載が認められていることも、適法である裏付けとなるでしょう。
実際に、バーチャルオフィスの住所で法人登記や特定商取引法に基づく表記を行う大手企業も多く存在します。
利用の仕方によって違法性が生じる可能性がある
バーチャルオフィスそのものは適法なサービスですが、利用の仕方によっては違法性が生じる可能性があります。具体的に違法性が生じるケースは、以下のとおりです。
- 詐欺やマネー・ローンダリングなどの犯罪行為を目的に利用する
- バーチャルオフィス事業者が犯罪収益移転防止法に基づく厳格な審査を実施していない
つまり、サービスやビジネスモデル自体に違法性はなく、バーチャルオフィスの仕組みを悪用する側の問題といえるでしょう。
なお、犯罪収益移転防止法とは、テロ資金供与やマネー・ローンダリングの防止などを目的に制定された法律です。バーチャルオフィスを含む特定の業種における入念な本人確認などが義務づけられています。
バーチャルオフィスが「怪しい」「違法」と誤解される背景
バーチャルオフィスが怪しい・違法と誤解される背景として、過去に犯罪目的での使用が多発したことが挙げられます。
バーチャルオフィスは法人登記が可能な住所を安価に取得でき、物理的なオフィスがないことから身元を隠しやすいという特徴があります。その特性から、詐欺やマネー・ローンダリング、ペーパーカンパニーの設立などに多く利用されました。犯罪の手段としてバーチャルオフィスが活用されたことから、「バーチャルオフィスは違法」というイメージがついたと考えられます。
しかし現在は、犯罪収益移転防止法によって、バーチャルオフィスの入会時には厳格な本人確認が義務づけられています。また、入会時に事業概要の確認や面談を実施しているバーチャルオフィス事業者も少なくありません。悪用目的でバーチャルオフィスを契約する者が未然に排除され、犯罪の手段として利用しづらくなりました。
犯罪目的でバーチャルオフィスを活用する者が減ることで、バーチャルオフィスは違法というイメージも払拭されつつあります。
【悪用事例】実際に違法となるケース
バーチャルオフィスの活用が実際に違法となるケースには、以下のようなものがあります。以下では、それぞれの事例について詳しく解説します。
- 法人登記詐欺・ペーパーカンパニーによる利用
- 架空請求・詐欺商法での利用
- 名義貸し的な利用
法人登記詐欺・ペーパーカンパニーによる利用
バーチャルオフィスには、法人登記詐欺やペーパーカンパニーの設立で利用される事例があります。
ペーパーカンパニーとは、法人登記はされているが、実際には活動していない書面上の会社のことです。ペーパーカンパニー自体は一概に違法とはいえません。しかし、脱税や詐欺で使われることが多く、ペーパーカンパニー=犯罪とイメージする方は少なくありません。
バーチャルオフィスは物理的なオフィスを持たず、低コストで利用できるという特徴があります。厳格な本人確認が行われなかった犯罪収益移転防止法の制定前は、ペーパーカンパニーを設立しやすい環境であったのです。
架空請求・詐欺商法での利用
バーチャルオフィスを利用して架空請求や詐欺といった犯罪行為を行う事例も少なくありません。
バーチャルオフィスの活用によって、実態のない企業を簡単に設立できます。さらに、一見信頼性が高い住所や電話番号を利用できるため、消費者が安心して取引をしてしまうのです。また、被害者が訴訟を起こしても、企業の実態がないことから賠償を受けるのが難しい点も、架空請求や詐欺で利用される理由となります。
名義貸し的な利用
バーチャルオフィスの契約者が第三者に名義を貸すような利用方法も違法となり得ます。
バーチャルオフィスの住所の第三者への名義貸しは、多くの場合で規約違反に該当しますが、違法とは断言できません。しかし、使われ方によっては詐欺罪や業務妨害罪、犯罪収益移転防止法違反などに該当する可能性があります。
名義貸しによって、詐欺などの犯罪行為を行った際に責任の所在を隠しやすくなります。適切な理由で名義貸しを行うケースはほとんどないため、バーチャルオフィスの名義貸しは悪用目的の可能性が高いといえるでしょう。
安心してバーチャルオフィスを利用するための注意点
トラブルに巻き込まれず、安心してバーチャルオフィスを利用するためには、以下の2点を確認しましょう。
- 適正な本人確認・審査を実施しないバーチャルオフィスとは契約しない
- 過去に犯罪や詐欺などに利用されたバーチャルオフィスとは契約しない
現在は、犯罪収益移転防止法の定めにより、入会時には厳格な本人確認や審査が義務づけられています。適正な本人確認や審査を実施していないバーチャルオフィスは違法であり、悪用目的で利用している者が存在する可能性があります。契約後にバーチャルオフィスが悪用されると、同じ住所を公開している自社の評判が著しく損なわれるため要注意です。
また、過去に犯罪などに利用されているバーチャルオフィスだと、自社の住所が検索された際に、犯罪の情報が見つかってしまいます。同様に自社の評判が損なわれる恐れがあります。事前に「バーチャルオフィスの住所+犯罪/詐欺」などで検索し、問題がない住所かを確認しましょう。
バーチャルオフィスの適法な活用事例
バーチャルオフィスの適法で代表的な活用事例は、以下の4つです。以下ではそれぞれの活用事例を詳しく解説します。
- ネットショップ運営の住所としての利用
- 個人事業主(フリーランス)の事業住所としての利用
- 営業拠点・支店住所としての利用
- 法人登記住所としての利用
ネットショップ運営の住所としての利用
バーチャルオフィスは、ネットショップの運営で多く利用されています。
ネットショップの運営を行う際は、特定商取引法の定めにより、事業所の住所や電話番号などをECサイトに公開する必要があります。自宅でネットショップを運営する場合、自宅住所の公開によるプライバシーのリスクが発生するため要注意です。
バーチャルオフィスを活用すれば、特定商取引法に基づく表記としてバーチャルオフィスの住所を公開できます。自宅住所を公開する必要がないため、安心してネットショップを運営できるでしょう。
また、バーチャルオフィスの郵便物の転送サービスを活用すれば、返品対応も円滑に進められます。さらに、電話番号をレンタルすれば、プライベートの電話番号を隠して特定商取引法に基づく表記が可能となります。
個人事業主(フリーランス)の事業住所としての利用
バーチャルオフィスは、主に自宅で仕事に取り組む個人事業主・フリーランスにも利用されています。
バーチャルオフィスの住所は、税務署に提出する開業届に記載することが可能です。個人事業主がバーチャルオフィスを活用すると、以下のようなメリットが生じます。
- 自宅住所の公開を防止でき、プライバシーを保護できる
- 都心一等地の住所により顧客や取引先に信頼感を与えられる
- 自宅を引っ越しても同じ住所を使い続けられる
- 将来的な法人化にもスムーズに対応できる
結果的に、不要なトラブルやリスク、面倒な手間を防止でき、取引先や顧客に安心して取引してもらえるようになります。
営業拠点・支店住所としての利用
バーチャルオフィスは営業拠点・支店住所としての利用にも適しています。
比較的手軽に事業用の住所を取得でき、契約を終えればすぐに利用を始められるため、首都圏や地方に試験的に進出できます。さらに、初期費用は数千円程度で、月額料金は数百円から数千円程度と非常に安価です。万が一首都圏・地方への進出に失敗しても損失を最小限に留められます。試験的な首都圏・地方進出に成功してから物理的なオフィスを取得するのも有効でしょう。
営業拠点を広げることで、その地域の顧客にアプローチしやすくなり、貸会議室を活用すれば対面での営業や商談も円滑に進められます。
法人登記住所としての利用
バーチャルオフィスの住所は、法人の本店所在地として登記が可能です。
バーチャルオフィスで法人登記を行うことで、一般的な賃貸オフィスと比べて大幅にオフィスコストを削減できます。賃貸オフィスでは契約が難しい都心一等地のオフィスを取得でき、対外的な信頼を得られる可能性があるでしょう。
一人会社の場合はもちろん、リモートワークを導入すれば小・中規模な企業でも十分に対応可能です。貸会議室や電話サービス、郵便サービスなどを活用すれば、事業運営のさらなる効率化を図れます。
ただし、一部のバーチャルオフィスでは、法人登記目的での利用を認めていないケースがあります。加えて、同一の住所(バーチャルオフィス)に同一商号の企業が存在すると、法人登記が認められません。契約前に、バーチャルオフィスの法人登記の可否や、同一商号の企業の有無を確認しましょう。同一商号の企業については、国税庁の「法人番号公表サイト」などを活用すれば調査できます。
バーチャルオフィスを選ぶ際のチェックポイント
自分に合ったバーチャルオフィスを選ぶためには、以下の点を比較検討しましょう。
- 料金が明瞭かつ予算内であるか
- 必要なサービス(郵便物の転送/電話サービスなど)が提供されているか
- 突然の来訪者に対応できるか(対面窓口や受付システムの有無)
- 法人登記が認められているか
- 利用規約が整っており、更新・解約条件が明確であるか
- 問い合わせに対するレスポンスは早いか
- 実際に立地やスタッフの顔を確認できるか
バーチャルオフィスの月額料金は「基本料金+オプション料金」で構成されています。基本料金に含まれる内容は各事業者で異なるため、基本サービスとそれぞれのオプション料金を必ず確認しましょう。
また、バーチャルオフィス事業者によっては法人登記が認められていないケースがあります。法人登記が可能でも上位プランへの加入や追加料金を求められる場合があるため、法人登記を目的とする場合は重要な確認事項です。
加えて、利用規約が整っていれば、契約後の不要なトラブルを避けられます。万が一トラブルが起きても、問い合わせに対するレスポンスが早ければ迅速に解決でき、安心感も生まれるでしょう。
バーチャルオフィスの選び方は、個々の用途や目的、事業形態などによって異なります。自身の希望に完全にマッチした事業者が見つかるとは限らないため、まずは利用目的や重視したいポイントを明確にすることが大切です。
まとめ
バーチャルオフィス自体は違法性がないサービスです。しかし、詐欺やマネー・ローンダリングなどに悪用されやすいという特性から、違法であると誤解している方も少なくありません。また、なかには犯罪収益移転防止法に違反した審査体制のバーチャルオフィスも存在します。
前提として、バーチャルオフィスを活用する際は、犯罪収益移転防止法に基づき厳格な本人確認や審査を実施している事業者を選択しましょう。迅速なレスポンスや対面での対応を受けられ、実際に建物を内見できればより理想です。
また、取引先や顧客がバーチャルオフィスの仕組みや適法性を理解していない場合は、しっかりと適法である旨を説明することが大切です。バーチャルオフィスを有効活用できれば、コスト削減やプライバシーの保護、第三者からの信頼性の向上につながるため、ぜひご検討ください。

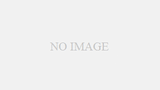
コメント