「電子帳簿保存法って、書類の種類が多くてどれが対象か分かりにくい…」と感じている方もいるでしょう。
「正しく保存しないと罰則があるって聞くし、不安だな…」と心配している方もいるかもしれません。
電子帳簿保存法は、令和4年1月の改正で大幅に変わりました。
知らないうちに法律違反になってしまう可能性もあるため、早いうちに内容を理解しておくことが重要です。
この記事では、電子帳簿保存法について改めて確認したい方に向けて、
– 電子帳簿保存法の対象書類一覧
– 電子帳簿保存法の保存要件
– 電子帳簿保存法の改正点
上記について、解説しています。
電子帳簿保存法は複雑で分かりにくい部分も多いですが、一つずつ確認していけば必ず理解できます。
この記事を読めば、電子帳簿保存法の対象書類や保存方法を正しく理解できるようになるでしょう。
ぜひ参考にしてください。
電子帳簿保存法の基礎知識を図解で理解
電子帳簿保存法は、企業が電子データで帳簿や書類を保存することを認めた法律です。これにより、紙の書類を保管するスペースやコストを削減できるだけでなく、業務効率の向上にもつながります。近年、電子取引の増加やペーパーレス化の推進により、ますます重要性を増していると言えるでしょう。
電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類の保存方法について定めています。具体的には、紙で保存する場合の要件、電子データで保存する場合の要件、スキャナ保存する場合の要件などを規定しています。これらの要件を満たしていない場合、税務調査の際にペナルティが課される可能性があるため、正しく理解しておくことが大切です。
例えば、電子データで保存する場合、データの改ざん防止や検索機能の確保など、一定の要件を満たす必要があります。具体的には、タイムスタンプの付与や訂正履歴の管理などが求められます。以下で、電子帳簿保存法の対象となる書類の種類や具体的な保存要件、そして近年における改正点について詳しく解説していきます。
電子帳簿保存法の3つの重要区分
電子帳簿保存法は、国税関係書類を電子データで保存することを認める法律です。大きく分けて「スキャナ保存」「電子取引」「電子計算機作成」の3つの区分があります。それぞれの区分で保存方法が異なるため、正しく理解することが重要です。
まず、「スキャナ保存」は、紙で受け取った書類をスキャナで読み取って保存する方法です。タイムスタンプの付与や検索機能の確保など、一定の要件を満たす必要があります。2022年1月1日以降に開始する事業年度からは、電子保存の承認申請が不要になりました。
次に、「電子取引」は、インターネットやメールでやり取りされる請求書や領収書などの保存に関する区分です。データ形式や保存方法に規定があり、紙への印刷保存は認められていません。改正電子帳簿保存法により、2024年1月1日以降は、受領者が保存した電磁的記録について、一定の要件を満たせば、送信者の保存義務がなくなります。
最後に「電子計算機作成」は、会計ソフトなどで作成される帳簿データの保存方法に関する区分です。こちらもデータ形式や保存期間が定められています。
電子帳簿等保存の概要
電子帳簿保存法は、国税関係書類を電子データで保存することを認める法律です。1998年に施行され、2022年1月には電子取引に関する宥恕規定が廃止されたため、対応が必須となっています。紙の書類を電子化して保存する場合、タイムスタンプの付与が必要です。また、電子データで受領した請求書などは、データのまま保存することが求められます。
電子帳簿保存法の対象となる書類は、大きく分けて3種類あります。1つ目は、仕訳帳や総勘定元帳などの「帳簿書類」です。2つ目は、請求書や領収書といった「取引関係書類」で、これらは法律で保存義務が定められています。3つ目は、契約書や見積書などの「関連書類」です。これらは法律上の保存義務はありませんが、保存を推奨されています。
これらの書類を電子保存する場合、いくつかの要件を満たす必要があります。例えば、検索機能を備えていること、データの改ざん防止措置を講じていることなどが挙げられます。具体的な要件は書類の種類によって異なるため、事前に確認が必要です。正しく理解し、適切な電子保存システムを導入することで、業務効率化やコスト削減を実現できるでしょう。
スキャナ保存の基本
電子帳簿保存法では、紙の書類ではなく電子データで保存することが認められています。この電子データ保存には、大きく分けて「スキャナ保存」と「電子取引」の2種類があります。今回は、スキャナ保存の基本について解説します。
スキャナ保存とは、紙でもらった領収書や請求書などをスキャナで読み取って画像データとして保存する方法です。電子帳簿保存法に対応したスキャナを用いれば、原本を破棄することも可能です。
スキャナ保存を行う際の注意点として、まず「タイムスタンプ」の付与が挙げられます。これは、いつ誰がスキャンしたかを証明するための電子的な印鑑のようなものです。改ざん防止のために必須ですので、必ず設定しましょう。次に、検索機能の確保も重要です。保存したデータは、日付や取引先などで検索できる状態にしておく必要があります。そのため、適切なファイル名で保存したり、検索システムを導入したりするなどの対策が必要です。最後に、データの保存期間にも注意が必要です。法律で7年間の保存が義務付けられていますので、適切な方法で保存・管理を行いましょう。
電子取引の義務化について
2022年1月1日より、電子帳簿保存法の改正により、電子取引に関するデータの保存が義務化されました。これまでは一部の企業に限定されていましたが、改正後はほぼ全ての事業者が対象となります。具体的には、請求書や領収書、契約書などの国税関係書類を電子データとして保存することが求められます。
従来の紙での保存も可能ですが、電子データでの保存を選択した場合、検索性や保存スペースの効率化といったメリットがあります。例えば、大量の書類の中から特定の請求書を探す際、日付や取引先名で簡単に検索できるようになります。また、書類の保管場所も不要になり、オフィススペースの有効活用につながります。
ただし、電子保存には一定の要件が定められています。例えば、データの改ざん防止や、取引年月日、金額などの検索機能が求められます。これらの要件を満たさないシステムを使用した場合、罰則が適用される可能性もあるため注意が必要です。具体的な要件については、国税庁のウェブサイトなどを参考に、適切なシステムを導入することが重要です。電子帳簿保存法への対応は、企業の効率化とコンプライアンスの両立に不可欠と言えるでしょう。
2024年改正で変わる電子帳簿保存法のポイント
2024年改正で変わる電子帳簿保存法のポイント
2024年1月1日から、電子帳簿保存法の改正点が施行されます。これにより、電子データでの保存がさらに促進され、企業の業務効率化が期待できるでしょう。特に、今回の改正では、電子取引に関する書類の保存方法が大幅に見直されています。これまで以上に、柔軟で効率的な運用が可能になるため、改正点を押さえておくことが重要です。
今回の改正の大きなポイントは、電子取引で受領した請求書等の保存要件の緩和です。具体的には、タイムスタンプの付与が不要になるケースが増えたり、検索機能の要件が緩和されたりしています。これらの変更によって、企業はシステム改修などの負担を軽減しつつ、法令に則った形で電子データを保存できます。
例えば、一定の要件を満たす「適格請求書発行事業者の登録番号」が記載された請求書は、タイムスタンプの付与が不要になります。また、従来必要だったデータの訂正・削除履歴の保存も、一定の条件下では不要になるケースがあります。以下で詳しく解説していきます。
電子取引データの紙保存要件変更
2022年1月1日より、電子取引データの紙保存要件が大きく変わりました。これまで義務付けられていた紙での保存が、一定の要件を満たせば不要になったのです。 これは、企業にとって業務効率化やコスト削減の大きなチャンスと言えるでしょう。
改正電子帳簿保存法では、電子データで保存する場合、データの改ざん防止や検索機能の確保など、いくつかの要件を満たす必要があります。具体的には、タイムスタンプの付与や訂正履歴の保存が求められます。また、取引先から受け取った請求書などの電子データも、同様に保存義務の対象となります。
これまで紙で保存していた企業は、システム改修などの対応が必要となる場合もあります。国税庁のウェブサイトでは、FAQや事例集など、役立つ情報が公開されているので、確認することをおすすめします。例えば、電子取引の範囲や具体的な保存方法などが詳しく解説されています。
適切な対応を怠ると、罰則が科される可能性もあるため、早めの対応が重要です。改正点や対応方法をしっかり理解し、スムーズな移行を実現しましょう。
スキャナ保存のタイムスタンプ緩和
電子帳簿保存法では、領収書や請求書などの国税関係書類を電子データで保存することが認められています。2022年1月1日より、電子データによる保存要件が一部緩和されました。特に注目すべき変更点は、スキャナ保存におけるタイムスタンプの要件緩和です。
従来、スキャナ保存を行う場合は、電子データにタイムスタンプを付与することが義務付けられていました。これは、改ざん防止のため、領収書等の受領日から起算して一定期間内にタイムスタンプを付与する必要があったのです。具体的には、受領日から7日以内にタイムスタンプを付与しなければなりませんでした。しかし、この要件が緩和され、受領日から3か月以内に付与すれば良くなりました。
この変更により、企業はタイムスタンプ付与のための事務作業負担を軽減できます。例えば、月末にまとめて領収書を処理する場合、7日以内という短期間でのタイムスタンプ付与は困難なケースもありました。しかし、3か月以内に延長されたことで、業務フローへの影響を最小限に抑えながら、法令を遵守することが可能になったと言えるでしょう。
ただし、タイムスタンプ要件が緩和されたとはいえ、電子帳簿保存法への適合は重要です。適切なシステムを導入し、社内規定を整備することで、スムーズな電子保存を実現し、税務調査にも適切に対応できる体制を整えましょう。
電子帳簿等保存で紙帳簿が不要に
電子帳簿保存法は、国税関係書類を電子データで保存することを認めた法律です。これにより、紙の帳簿を保管する必要がなくなりました。平成10年に施行され、令和4年には大幅な改正が行われ、電子取引に関する書類の保存義務化など、企業のデジタル化を後押しする制度となっています。
具体的には、請求書や領収書、契約書といった国税関係書類を電子データで保存することが可能です。これにより、書類の保管スペースが削減できるだけでなく、検索も容易になります。結果として、業務効率化やコスト削減に大きく貢献するでしょう。
ただし、電子保存には一定の要件が定められています。例えば、データの改ざん防止や検索機能の確保などです。これらの要件を満たしていないと、税務調査の際にペナルティを受ける可能性があるので注意が必要です。
対象となる書類は多岐に渡ります。請求書、領収書、契約書以外にも、見積書や納品書なども含まれます。自社の業務で扱う書類が対象かどうか、事前に確認することが重要です。
事業者が取るべき対応策
事業者が取るべき対応策
電子帳簿保存法に対応するためには、まず自社がどの書類をどのように保存する必要があるのかを正しく理解することが重要です。保存対象となる書類の種類や保存方法は法律で定められていますので、しっかりと確認しましょう。そして、現状の保存方法が電子帳簿保存法の要件を満たしているかどうかの確認も必須です。
電子帳簿保存法への対応は、単に書類を電子化するだけでなく、適切なシステムの導入や運用体制の整備も必要となります。例えば、電子データの改ざん防止や検索性の確保など、法令で求められる要件を満たすシステムを選ぶことが大切です。また、従業員への教育も不可欠です。適切な運用ルールを策定し、従業員が正しく運用できるよう教育することで、法令違反のリスクを低減できます。
具体的には、2024年1月1日からの電子取引に関する宥恕規定の廃止を踏まえ、対応が遅れている企業は早急に電子保存の体制を整えるべきでしょう。例えば、電子保存に対応した会計ソフトの導入や、スキャナ保存を行う際のタイムスタンプの付与などを検討する必要があります。以下で詳しく解説していきます。
電子取引の現状確認と改善
電子帳簿保存法は、国税関係書類を電子データで保存することを認めた法律です。2022年1月1日からは、電子取引に関する書類の保存が義務化されました。これにより、紙の請求書や領収書の発行、郵送、保管にかかるコストや手間を削減できるようになりました。
電子取引の対象となる書類は、見積書、契約書、注文書、納品書、請求書、領収書など、取引に関する書類全般です。これらの書類を電子データで保存する場合、いくつかの要件を満たす必要があります。例えば、データの改ざん防止、検索機能の確保などが求められます。具体的な要件は、国税庁のウェブサイトなどで確認できます。
自社の電子取引の現状を確認し、法令に適合しているか、業務効率化の余地がないかを検討することが重要です。例えば、電子取引に対応していない取引先がある場合、対応を依頼する、あるいは電子取引に対応したシステムを導入するなどの改善策が考えられます。また、すでに電子保存している場合でも、検索機能が不十分だったり、データの保存期間が適切でなかったりする場合は、システムの見直しが必要です。適切な電子保存によって、業務効率化だけでなく、コンプライアンス強化にも繋がります。
業務フローの再設定
電子帳簿保存法では、紙の書類だけでなく電子データも保存対象となります。請求書や領収書はもちろん、契約書や見積書なども対象になることをご存知でしょうか。これらを適切に保存していないと、税務調査でペナルティを受ける可能性があります。
そこで重要なのが、業務フローの見直しです。まず、現状のフローを可視化し、どの書類が電子データで、どの書類が紙媒体で保存されているかを確認しましょう。例えば、領収書は経費精算システムで電子化されている一方、契約書は紙で保管されているケースが多いかもしれません。
次に、電子帳簿保存法の要件に基づき、各書類の保存方法を最適化していきます。具体的には、スキャナ保存、電子取引データの保存、タイムスタンプの付与など、適切な方法を選択する必要があります。2024年1月からは、電子取引データの保存において、受領者がタイムスタンプを付与する義務がなくなりました。この変更点も踏まえ、自社のシステムや運用方法を見直すことが大切です。
例えば、これまで紙で受け取っていた請求書をPDFで受け取るように変更すれば、電子データとして保存できます。このように、小さな変更を積み重ねることで、法令遵守と業務効率化を両立できるはずです。
適切なデータ保存システムの構築
電子帳簿保存法では、請求書や領収書といった国税関係書類を電子データで保存することが認められています。 これはペーパーレス化によるコスト削減や業務効率化に大きく貢献しますが、適切なデータ保存システムの構築が不可欠です。
具体的には、電子データの改ざん防止、検索機能の確保などが求められます。 例えば、タイムスタンプの付与によって、データが作成された日時を証明できます。これにより、後からデータが改ざんされていないことを証明できるのです。また、書類の取引日付や取引先名などで検索できるシステムを導入すれば、必要な書類をすぐに見つけることが可能になります。
さらに、電子帳簿保存法では、領収書を電子データで受け取る場合、受領者の同意と、データの訂正削除履歴を7年間保存することが義務付けられています。これらの要件を満たしていないと、電子保存の効力が認められず、税務調査の際にペナルティを受ける可能性も出てきます。
2024年1月からは、電子取引におけるインボイス制度も開始されます。 この制度も電子帳簿保存法と密接に関連しているため、両制度の要件を理解した上で、適切なデータ保存システムを構築することが重要となるでしょう。
電子帳簿保存法の対象となる書類一覧
電子帳簿保存法の対象となる書類一覧
電子帳簿保存法は、企業が電子的に書類を保存することを認める法律ですが、すべての書類が対象となるわけではありません。対象となる書類の種類を正しく理解しておくことは、コンプライアンスの観点から非常に重要です。この見出しでは、電子帳簿保存法の対象となる書類を一覧でわかりやすくご紹介します。
電子帳簿保存法の対象となる書類は、大きく分けて「国税関係帳簿書類」と「取引関係書類」の2種類に分類されます。国税関係帳簿書類とは、法人税や所得税、消費税などの申告に用いる帳簿や書類のことです。例えば、仕訳帳や総勘定元帳、貸借対照表などが該当します。一方、取引関係書類とは、取引に関する書類で、具体的には請求書や領収書、契約書などが該当します。これらの書類は、税務調査の際に必要となる可能性があるため、適切に保存することが求められます。
例えば、あなたが企業の経理担当者だとします。取引先から受け取った請求書を電子データとして保存する場合、電子帳簿保存法の要件を満たしていなければ、税務調査の際に認められない可能性があります。具体的には、タイムスタンプの付与や改ざん防止措置などが必要となります。これらを怠ると、ペナルティを受ける可能性もあるため、注意が必要です。以下で、それぞれの書類について詳しく解説していきます。
電子帳簿等保存対象の帳簿と書類
電子帳簿保存法では、電子データによる保存が義務付けられている帳簿書類がいくつかあります。具体的には、2022年1月1日以降、すべての企業で適用されるようになった「電子取引」に関する書類が該当します。
電子取引とは、インターネットやメールなどを利用した取引のこと。受発注書、請求書、領収書などが代表的な例です。これらの書類は、紙で受け取ったとしてもスキャンして電子データとして保存しなければなりません。
一方で、法律で電子保存が義務付けられていない書類も存在します。例えば、従業員の給与明細書、株主総会議事録、契約書などが挙げられます。これらの書類は紙での保存でも問題ありませんが、電子保存を選択することも可能です。
ただし、電子保存する場合は、法律で定められた要件を満たす必要があります。具体的には、検索機能の確保やデータ改ざんの防止策などが求められます。これらの要件を満たさないまま電子保存を行うと、税務調査の際にペナルティを受ける可能性があるので注意が必要です。
スキャナ保存対象の書類
スキャナ保存で電子帳簿保存法に対応するには、対象書類を正しく理解することが重要です。具体的には、領収書や請求書といった取引に関する書類はもちろん、契約書や見積書なども含まれます。これらの書類は、法律で定められた要件に従ってスキャナ保存しなければなりません。
例えば、領収書の金額が3万円未満の場合、従来は紙での保存が義務付けられていましたが、2022年1月1日以降は電子保存も可能になりました。ただし、タイムスタンプの付与など、一定の要件を満たす必要があります。
また、請求書は金額に関わらず電子保存が可能ですが、こちらも同様に適切な方法で保存しなければなりません。具体的には、電子署名やタイムスタンプの付与が必要です。これらの要件を満たしていない場合、税務調査の際にペナルティを受ける可能性があります。
さらに、契約書や見積書といった書類も、取引に関連する重要な書類として電子保存の対象となります。これらの書類も、適切な方法で保存することで、ペーパーレス化による業務効率の向上に繋がります。そのため、電子帳簿保存法の対象書類を正しく理解し、適切な保存方法を選択することが重要です。
電子取引対象の書類
電子帳簿保存法では、電子取引で授受した書類も電子データで保存することが義務付けられています。具体的には、見積書、注文書、契約書、納品書、請求書、領収書などが該当します。これらの書類は、紙で受け取った場合でもスキャンして電子データとして保存することが可能です。
従来、これらの書類は7年間の保存が義務付けられていましたが、令和4年1月1日以降に開始する事業年度からは、電子データでの保存であれば、保存期間の制限はなくなりました。ただし、検索機能などを備えた適切な方法で保存する必要があります。
電子取引で授受した書類を電子保存するメリットは、保管スペースの削減や検索性の向上だけではありません。ペーパーレス化による業務効率の改善、印紙税の削減といったメリットも享受できます。例えば、年間300件の契約を締結する企業が電子契約に移行した場合、年間で30万円もの印紙税を節約できる可能性があります。また、書類の紛失リスクを軽減できる点も大きなメリットと言えるでしょう。
電子帳簿保存法の保存要件を詳しく解説
電子帳簿保存法の保存要件を詳しく解説
電子帳簿保存法では、電子データで保存する場合、いくつかの要件を満たす必要があります。これらの要件を正しく理解していないと、税務調査の際に思わぬ指摘を受ける可能性がありますので、注意が必要です。このセクションでは、保存形式、可視性、検索機能、そして訂正・削除履歴の保存という4つの主要な要件について解説します。
電子帳簿保存法では、国税関係帳簿書類を電子データで保存する場合、データ形式、見読性、検索機能、訂正・削除履歴の保存という4つの要件を満たさなければなりません。これらの要件を満たしていないと、電子データによる保存は認められず、紙での保存が必要となる場合もあります。また、税務調査の際にもスムーズな対応ができなくなる可能性がありますので、しっかりと理解しておくことが重要でしょう。
例えば、保存形式については、PDF、Word、Excelなどの一般的な形式に加え、タイムスタンプ付きの電子署名が必要です。具体的には、電子署名は書類の真正性を確保するために必要であり、タイムスタンプは書類の作成日時を証明するために不可欠です。以下で詳しく解説していきます。
電子帳簿等保存の要件
電子帳簿保存法では、国税関係書類を電子データで保存する場合、いくつかの要件を満たす必要があります。具体的には、電子データの真実性を確保するための「訂正・削除履歴の保存」や、データの検索性を高めるための「検索機能の確保」などが挙げられます。また、保存するデータの内容が確認できるよう、「可視性の確保」も求められます。これらの要件を満たしていないと、電子保存の効果が認められないため、注意が必要です。
例えば、請求書を電子データで保存する場合、誰がいつ、どの部分を訂正・削除したのかが分かる記録を残しておく必要があります。また、取引先名や日付などで検索できる機能を備えていなければなりません。さらに、保存したデータの内容を画面に表示したり、印刷したりできる状態にしておくことも重要です。
これらの要件は、2022年1月1日以降に開始する事業年度から適用される電子帳簿保存法の改正で、さらに厳格化されています。例えば、電子取引で受領した請求書については、データ形式の変更が原則として認められなくなりました。そのため、企業はシステム改修など、対応が必要となるケースもあります。事前にしっかりと確認し、適切な対応を行いましょう。
スキャナ保存の具体的要件
電子帳簿保存法では、スキャナ保存を行う場合、いくつかの要件を満たす必要があります。これらの要件を正しく理解し、適切な保存方法を採用することで、罰則や追徴課税のリスクを回避できます。
まず、重要な要件の一つとして「タイムスタンプ」の付与が挙げられます。タイムスタンプとは、電子データがいつ作成・変更されたかを証明する電子的な印です。これは、データの真正性を確保するために必須であり、改ざん防止に役立ちます。具体的には、電磁的記録に記録された時刻から1秒以内に付与する必要があります。
次に、「検索要件」への適合も重要です。保存した電子データは、事業年度、取引年月日、取引先などの項目で容易に検索できる状態にしておく必要があります。例えば、請求書をスキャン保存する場合、請求日や取引先名で検索できるシステムを構築することが求められます。
さらに、電子帳簿保存法では、帳簿書類の保存期間が7年間と定められています。そのため、スキャナ保存を行う場合も、この期間にわたりデータの完全性を維持しなければなりません。定期的なデータバックアップやシステムのメンテナンスは必須と言えるでしょう。例えば、外付けハードディスクやクラウドストレージを活用し、複数箇所にデータを保存することで、データ消失のリスクを軽減できます。
これらの要件を満たさない場合、電子帳簿保存法違反となり、罰則や追徴課税が課される可能性があります。適切なスキャナ保存を実施し、コンプライアンスを徹底しましょう。
電子取引の保存要件
電子取引で受け取った請求書や領収書。これらを紙で印刷して保管している企業も多いのではないでしょうか。しかし、電子帳簿保存法では、一定の要件を満たせば電子データのまま保存することが認められています。これが電子取引の保存要件です。
具体的には、データの真正性を確保するためのタイムスタンプや、検索機能の確保などが求められます。例えば、請求書をPDFで受け取った場合、そのままでは改ざんされるリスクがあります。そこで、タイムスタンプを付与することで、データが受信した時点から変更されていないことを証明できるのです。また、必要に応じて速やかにデータを見つけられるよう、適切な検索機能を備えたシステムで保存する必要もあります。
これらの要件を満たさないまま電子データを保存すると、税務調査の際にペナルティが課される可能性があります。2022年1月からは電子取引に関する保存要件が強化されましたので、改めて自社の保存方法を見直すことが重要です。国税庁のウェブサイトには、電子帳簿保存法に関する詳細な情報が掲載されています。そちらも参考に、適切な保存方法を検討しましょう。
電子帳簿保存法に関するよくある質問
電子帳簿保存法に関するよくある質問
電子帳簿保存法について、様々な疑問を持つ方もいるでしょう。このセクションでは、よくある質問とその回答をまとめ、制度への理解を深めていただくための情報を提供します。具体的な内容を理解することで、電子帳簿保存法をスムーズに運用できるようになるでしょう。
よくある質問としては、例えば「電子帳簿保存法の対象となる書類は何ですか?」や「保存期間は何年ですか?」、あるいは「電子保存する場合の要件は何ですか?」といったものがあります。これらの質問は、企業規模や業種に関わらず多く寄せられるもので、制度の重要なポイントと言えるでしょう。特に2024年1月1日からの改正点に関する質問も増えており、対応に不安を感じている方もいるかもしれません。
以下で、これらのよくある質問と回答を詳しく解説していきます。具体的な事例を交えながら、わかりやすく説明しているので、ぜひ参考にしてください。
電子帳簿保存法の対象企業について
電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類を電子データで保存することを認める法律です。2024年1月1日からは、電子取引に関する宥恕規定が廃止されるため、事実上すべての企業が電子帳簿保存法の対象となります。これまで適用除外だった売上高10億円未満の企業も、電子取引を行っていれば対象になるため、注意が必要です。
具体的には、請求書、領収書、契約書などの国税関係書類を電子データで保存することが義務付けられます。これまでは紙で保存していた企業も、電子データでの保存に切り替える必要が出てくるでしょう。
対象となる書類は、大きく分けて「取引に関する書類」と「帳簿書類」の2種類です。取引に関する書類には、請求書、領収書、見積書などが含まれます。帳簿書類には、仕訳帳、総勘定元帳などが該当します。これらの書類を適切に電子保存するには、システム対応や運用ルールの見直しが必要になるケースもあります。例えば、タイムスタンプの付与や検索機能の確保など、要件を満たしたシステムを導入しなければなりません。
改正電子帳簿保存法への対応は、企業規模に関わらず必須です。早めの対応で、スムーズな移行を実現しましょう。
個人事業主の対応策
電子帳簿保存法は、2024年1月1日から改正され、個人事業主にも影響が出ます。特に、電子取引で受け取った請求書や領収書は、データでの保存が義務化されました。これまでは紙で保存するか、スキャナ保存であればタイムスタンプが必要でしたが、改正後はこれらの要件が撤廃されます。ただし、検索性に優れた状態で保存することが求められます。具体的には、日付、金額、取引先で検索できる必要があります。
対応策としては、クラウド会計ソフトの導入がおすすめです。freeeやマネーフォワードクラウド会計などのソフトは、電子帳簿保存法に対応しており、電子データの保存や検索を簡単に行えます。これらのソフトは、銀行口座やクレジットカードと連携でき、自動で取引データを取り込んでくれます。また、領収書をスマートフォンで撮影して保存する機能も備わっており、ペーパーレス化も実現できます。
もし会計ソフトを導入しない場合は、PDFで保存し、適切なファイル名で管理することが重要です。例えば、「20240401_株式会社A_請求書_100000円」のように、日付、取引先、書類の種類、金額をファイル名に含めることで、検索性を高めることができます。また、エクセルで管理台帳を作成し、PDFの保存場所を記載する方法も有効です。
電子取引未対応の影響
電子取引は、電子帳簿保存法の改正で対応が必須となったわけではありません。しかし、対応していないと様々なデメリットが生じます。紙の請求書を電子データとして保存する場合、タイムスタンプの付与など、手間とコストがかかります。PDF化の手間や、検索性の低さも大きな問題です。
具体的には、2024年1月1日以降、紙の請求書をスキャン保存する場合、検索要件を満たす必要があります。そのためには、日付、金額、取引先といった項目を、システム上で検索できる状態にしなければなりません。紙の請求書を一枚一枚確認しながらシステムに入力していく作業は、非常に非効率です。また、電子取引に対応していないと、取引先とのデータ連携もスムーズに進みません。取引先が電子データで請求書を送信してきた場合、自社で印刷して保管することになり、電子化のメリットを享受できません。
これらを踏まえると、電子帳簿保存法への対応は、電子取引への対応を同時に行うのが効率的と言えるでしょう。電子取引に対応することで、業務効率化、コスト削減、ペーパーレス化といったメリットを享受できます。DX推進の流れが加速している昨今、電子取引への対応は企業にとって必須と言えるのではないでしょうか。
まとめ:電子帳簿保存法を理解して、業務効率化を実現しましょう
今回は、電子帳簿保存法について詳しく知りたいと考えている経営者や経理担当者の方に向けて、
– 電子帳簿保存法の対象書類
– 電子帳簿保存法の保存要件
– 電子帳簿保存法の改正点
上記について、解説してきました。
電子帳簿保存法は、企業の会計処理を電子化し、ペーパーレス化を進める上で重要な法律です。
この法律を正しく理解することで、業務効率化やコスト削減を実現できるでしょう。
もしかしたら、電子帳簿保存法について複雑で分かりにくいと感じている方もいるかもしれません。
しかし、本記事で解説した内容を参考に、一つずつ確認していくことで、必ず理解を深められるはずです。
今まで電子帳簿保存法について知らなかった方も、本記事を通して新たな知識を得ることができたのではないでしょうか。
電子帳簿保存法を正しく理解し、活用することで、あなたの会社は必ず成長できるでしょう。
まずは、自社の状況に合わせて、電子帳簿保存法への対応を進めてみてください。

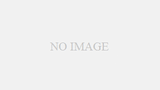
コメント